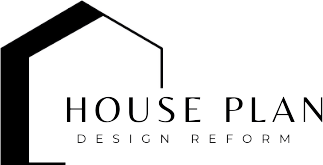部屋をどこに配置するか、レイアウトは快適な暮らしになるかどうかを大きく左右します。本格的な図面は、建設会社や設計士が行ってくれるとはいえ、理想の家や要望を明確にして伝えるためには、ある程度自分なりに間取りを考えておく必要があります。しかし、あまりにも漠然としすぎて、何をどこから始めれば良いのか分からないという方は少なくありません。
建設会社やリフォーム会社に要望を伝えるうえでも大切な、理想の間取りをカタチにする方法や考え方をプロの設計士がご説明したいと思います。
1.ゾーニングでイメージをカタチに!
間取りをカタチにするために、まずは何から手をつけると良いのでしょうか?図面を書けない人でも出来る間取りの決め方をご紹介したいと思います。
■イメージをカタチにするゾーニング
始めから細かく部屋を区切って考えて間取りを作っていくのは難しいため、まずはプロも使う『ゾーニング』という方法を使いましょう。
ゾーニングとは、住まいの空間をゾーンごとに分けて考える手法です。一般的な住宅のゾーンとして下記に分けることが出来ます。
●パブリックゾーン:リビングやダイニングなど、家族や来客者が利用する空間です。リビングとダイビングを一体化するか、別にするか、客間を設けるかどうかなど、ゾーンをさらに細かく分けて考えることも出来ます。
●プライベートゾーン:子供部屋や寝室、書斎、ワークスペースなど、家族それぞれの個別の空間です。書斎や趣味室、ワークスペースなどは特に、各家庭によって必要かどうかが異なり、ライフスタイルによって違いが出る部分です。
●サービスゾーン:キッチンや浴室、洗面脱衣所、トイレなどの水回りがメインとなる日常生活に欠かせない空間です。家事導線に特に影響が出る部分です。
●通路ゾーン:廊下や玄関ホール、階段などの各ゾーンをつなぐ移動するための空間です。通路ゾーン以外を最大限に確保するために廊下の無い家にしたり、階段のない平屋にしたりと、他のゾーンや構造に合わせて調整しやすい空間です。
基本的に上記の4つのゾーンが必要となるということを理解しておくと、大まかに空間を分けて考えることができます。
■ゾーニングを視覚化しよう!
建築の知識がない人は、初めから間取り図を描くのは難しいものです。そのため、まずは空間のイメージを視覚化することを意識しましょう。それぞれのゾーンに何を求めるかを箇条書きにして、理想を明確化していくことも大切です。
そのうえで白紙に、上記の4つのゾーンを〇や□で大まかに配置するところからスタートしてみましょう。まずは、家族が集まるパブリックゾーンを中心に置いて描いてみます。そして、どのゾーンを隣り合わせにすると良いか、4つを比較して、どこを広くしたいか、割合を視覚化することで、優先順位なども考えやすくなります。
ゾーニングを描く際には、始めから広さや細かな寸法を意識してカタチにしようとするのではなく、ゾーンのレイアウトを意識して、ラフに配置していくことがポイントです。
2.ゾーニングをより具体的にする3ステップ
ゾーニングを決めたうえで、より自分の暮らしに合わせた間取りにするために、どのように具体的にしていくと良いのでしょうか?3ステップをご説明したいと思います。
ステップ1:必要な部屋数・広さを考える
まずは、4つの大まかなゾーンの中で必要な部屋の名称、例えば、プライベートゾーンであれば、寝室1つ、子供部屋2つ、書斎1つ、というように、自分の家に必要な部屋と数を記載しましょう。各ゾーンの中でさらにどれだけ区切る必要があるのかを理解しやすくなります。
4つのゾーンをレイアウトしたうえで、各ゾーン内にある部屋を分解するようにわけていくと、自ずと部屋のレイアウトがカタチになってきます。
さらに部屋ごとにレイアウトしたうえで、理想とする各部屋の広さも決めて記入しておきましょう。
ステップ2:立地環境・構造に当てはめる
大体の部屋の配置を決めたうえで、次は立地環境や敷地のカタチ、理想とする構造、方角に照らし合わせて、微調整をしていきます。
例えば、道路の位置で玄関の位置を絞り込んだり、太陽があたる場所にリビングやバルコニー、ランドリールームを配置したり、ゾーンをパズルのように動かしながら調整していきましょう。調整する際には、各ゾーンに箇条書きにしている、ゾーンに求めることや優先順位と照らし合わせることで、理想のレイアウトに近づけることが出来ます。
また、マンションであれば、玄関やベランダ、窓の位置は決まっているので、固定してゾーンを動かしてみましょう。戸建てであれば、庭や駐車場など外回りのゾーンも大まかに書き加えておきましょう。
ステップ3:我が家ならではの暮らしに合わせる
最後に配置したゾーンを自分たちのライフスタイルと照らし合わせます。家族全員の日々の動きをレイアウト上で確認してみましょう。居場所がないと感じることはないか、それぞれのプライベートゾーンは守られているか、パブリックゾーン以外で、重なるゾーンや時間帯があって使いにくくなっていないか、などが確認できます。
例えば、プライベートゾーンとサービスゾーンが近くて導線が短く便利になっていても、睡眠時間や仕事の時間に他の家族がサービスゾーンにいて、音が聞こえやすくうるさくなりそうな場合は、少し離してレイアウトすると良いかもしれません。また、朝に洗面所に家族が集中するなら、サービスゾーンや通路ゾーンを広くとったり、1階と2階の両フロアにゾーンを確保したりするといった、暮らしに合わせた工夫が出来ます。
建設会社やリフォーム会社に要望を伝える際には、上記の3つのステップをベースに描いたレイアウト図を使って説明すると理想が伝わりやすくなります。また、設計士は、それをベースに寸法を合わせて図面に出来るので、スムーズに打ち合わせを進めることが出来て便利です。仮に、納得のいくレイアウトや、解決探が見つからない場合でも、レイアウトした紙に問題点を記入しておくことで、プロに依頼した時に、注意して良い方法を考えてくれます。
3. まとめ
大まかに間取りのレイアウトを決めておくと、理想の暮らしを伝えやすくなり、打ち合わせがスムーズに行えます。図面を描くことが出来なくても、ゾーニングによってレイアウト決めを行うことが可能です。まずは、パブリックゾーン、プライベートゾーン、サービスゾーン、通路ゾーンの4つのゾーンをラフにレイアウトしましょう。各ゾーン内に、必要な部屋数や広さ、ゾーンに求める要望などを記載しておけば、イメージをカタチや文字で視覚化しておくことが出来ます。さらに、立地環境や構造、自分たちのライフスタイルに合わせてレイアウトを調整していくことで、より具体的で現実的な間取りに近づけることができます。
ゾーニングという手法を使って、理想のイメージをカタチにしていきましょう!